壁に背中を合わせた。クラスの方ではまだ声が聞こえている。
寒さがひどくなってから、マフラーも制服の一部として定着し始めていた。私の首にもそれは巻かれていて寒さを少しずつ和らげていた。がたがた、という音がして何人かが教室から出てくる。目をやると、掃除を終えた男の子たちがいた。
「おー!やん、白石待ってるんか!」
ふふ、と肯定を含めて微笑って返す。
「はよ帰れよ白石ー!」
けらけらと笑いながら走っていく男の子たちに背を向けて、教室を覗くと蔵が箒を片付けているところだった。
テニスバッグを背負って私の隣に並ぶ。
「ほな、行こうか」
「うん」
少しずつ踏み出す足先は付き合った当初よりも鈍くなったかもしれない。元々、付き合ったからといって私達は変わりはしなかった。
こうして蔵を待って、蔵が私を待つ。蔵は先に帰ってて、なんて言わなかった。
だから、私も先に帰って、とは言わない。
「今日はな、謙也が金ちゃんと昼飯奪いあっとってん」
「蔵は奪われなかったの?」
「おん、大丈夫やで」
少しだけの会話を交わして、お互いの家まで帰る。毎日がその繰り返しで、
変わらない。
私は蔵の望む甘い言葉を囁いてあげられるような性分ではない。
蔵も見た目よりか思っていることを言葉にするということをしようとはしない。
それでも私達がこうして居られるのは、言葉よりか確かに繋がれた右手があるからだろう。ただお互いを見て微笑うことしか出来ないけれど、何も不自由はない。
「もう、冬やな」
「うん。寒くなるね」
「俺も今度からマフラーしようかなあ」
「黒いチェックの?」
「よう覚えてるなあ」
蔵が柔らかく笑う。そうだねと私も笑った。
また静かに、ただゆっくりと歩を進める。いつもと同じ道に、いつも同じような会話。変わらない私達に、優しさを求めるように繋いだ右手が少しだけ強くなった。
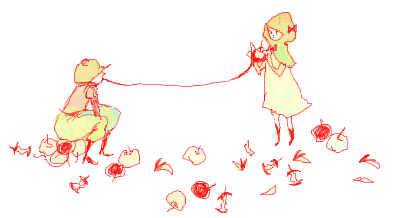
2012.2.12